皆さんこんにちは。宮城県仙台市を拠点に、店舗建築や戸建て新築、マンションリノベーション等を手掛けているアート株式会社です。
2025年4月1日、建築基準法の改正が施行されます。この改正は建築業界全体に大きな影響を与え、設計や施工の基準が見直されることとなります。特に、省エネ基準の義務化範囲の拡大や建築確認申請の簡略化、木造建築に関する規制の変更など、実務に直結する内容が多く含まれています。建築士や施工業者の方々にとって、これらの変更点を正しく理解し、適切に対応することが求められます。
本記事では、建築法改正の背景や目的を整理し、具体的な改正内容と業界への影響について詳しく解説します。さらに、改正後に建設業界が直面する課題と、それに対する対応策についてもご紹介します。建築物の安全性向上や省エネルギー化、合理化が求められる中、どのように対応すべきかを考えるための参考として、ぜひ最後までご覧ください。
2025年建築法改正の概要

建築法改正の背景と目的
建築基準法改正の経緯
建築基準法は、建築物の安全性や利便性を確保するために制定され、社会の変化に応じて改正が繰り返されてきました。近年、耐震性や省エネ性能の向上が求められる中、現行の基準では対応しきれない部分が指摘されていました。特に木造建築の構造計算や防火基準の見直し、省エネ性能の向上に関する議論が進められ、2025年の改正に至りました。
社会的要請(脱炭素・省エネ・安全性向上)
近年、建築分野において脱炭素化の推進が求められています。建築物のエネルギー消費を抑えるため、断熱性能の強化や再生可能エネルギーの活用が重視されるようになりました。また、災害に強いまちづくりを推進する観点から、建築物の耐震性や防火性能の向上も不可欠です。こうした背景を受け、建築基準法の改正によって、省エネ基準の厳格化や耐震基準の見直しが行われることになりました。
国土交通省の方針と施行スケジュール
国土交通省は、2025年4月1日を施行日として建築法改正を実施する予定です。この改正では、省エネ基準の適用範囲を拡大するとともに、建築確認申請の合理化が進められます。事業者や建築士は、新たな基準に適合した設計・施工を求められるため、早めの対応が重要になります。
主な改正ポイントと適用範囲
建築物の設計・施工における変更点
今回の改正では、建築物の安全性や省エネ性能を向上させるために、設計や施工の基準が見直されます。特に、木造建築の構造計算が義務化されることで、強度の確認がより厳格になります。また、9mを超える建築物に対する防火基準の強化や、小規模建築物の省エネ基準適用範囲の拡大も実施されます。
建築確認申請の手続き簡略化
従来の建築確認申請手続きについて、一部手続きの合理化や添付図書の簡略化(仕様規定で構造安全性を確認する場合など)が進められる一方、これまで審査が一部省略されていた小規模建築物(旧4号建築物の一部)では構造関係規定等が新たに審査対象となるなど、手続きや審査内容が見直されます。
省エネ基準の義務化範囲の拡大
省エネ基準の適用対象が拡大され、今後はより多くの建築物において省エネ性能の向上が求められます。これにより、住宅や商業施設のエネルギー消費量削減が促進され、持続可能な社会の実現に貢献することが期待されます。設計や施工に関わる事業者は、新たな基準に適合する設備や建材の導入を検討する必要があります。
具体的な改正内容と業界への影響

木造建築に関する変更点
4号特例の見直しと構造計算の義務化
これまで建築確認時の審査が一部省略されていた小規模な木造建築物(4号建築物)について、その対象範囲が見直され、多くが「新2号建築物」または「新3号建築物」に区分されます。特に、木造2階建てや平屋建て延べ面積200㎡超(新2号建築物)では、構造関係規定(壁量計算、柱の小径計算等)や省エネ基準への適合確認が必要となり、関連図書の提出が求められます。さらに、延べ面積300㎡を超える木造建築物については、許容応力度計算等の構造計算が義務化されます。これにより、建築士や施工業者にとっては、設計・審査への対応が必要になります。
壁量計算の変更と安全性確保
壁量計算の基準が改正され、地震や強風に対する安全性が向上します。これにより、木造建築物の耐震性能や耐風性能が厳しく審査されるようになります。特に住宅の設計では、従来よりも多くの壁量を確保する必要があり、施工方法の見直しが求められます。
木材活用の促進と規制緩和
国の脱炭素政策の一環として、建築物における木材の利用が促進されます。一定規模の非住宅建築物において木造建築が認められる範囲が拡大し、木材の利用を促進する制度が整備されます。これにより、木造建築の市場が拡大し、新たな設計手法や建材の活用が期待されます。
高さ・延べ面積・防火基準の変更

9mを超える建築物の規制変更
従来、高さ9mを超える木造建築物には厳しい規制がありましたが、今回の改正で緩和が進みます。これにより、中層木造建築の実現が容易になり、都市部においても木造建築の選択肢が広がる可能性があります。ただし、構造強度や防火性能の確保が必要となるため、適用条件の確認が求められます。
2階建て住宅の防火基準の見直し
建築物全体の防火安全性能向上のため、防火地域・準防火地域内外における木造建築物の防火に関する規定が見直されます。例えば、一定の防火措置を講じることで、従来は難しかった木材を内装や外装に「現し(あらわし)」で利用することが可能になるなどの合理化が行われる一方、大規模・中層建築物を中心に、要求される耐火性能や防火区画に関する基準が一部変更されます。設計・施工においては、最新の基準に適合した材料や工法を選定する必要があります。
大規模建築物の適合基準強化
大規模な建築物に対しては、耐火性能や避難経路の確保などの適合基準が強化されます。これにより、従来の建築基準では認められていた設計や施工方法に変更が求められるケースが増えることが予想されます。
省エネ基準とエネルギー消費削減の影響
省エネ法改正による義務化の範囲拡大
省エネ基準の義務化が拡大され、これまで対象外であった小規模建築物にも適用されます。住宅や小規模店舗においても、エネルギー消費量の削減を目的とした設計が求められ、断熱性能の向上や高効率設備の導入が必須となります。
設備仕様の変更と省エネ計画策定義務
建築物に使用される設備の仕様が見直され、高効率な設備の導入が義務付けられます。これにより、給湯・空調・照明といった設備の仕様を変更する必要が生じ、省エネ計画の策定が求められます。事業者は、設備の選定において法令の適合性を確認する必要があります。
省エネ住宅に対する補助金・優遇措置
省エネ基準に適合した住宅には、補助金や税制優遇措置が適用される可能性があります。これにより、省エネ住宅の普及が促進され、住宅市場において省エネ性能の高い建物の需要が拡大することが予想されます。住宅購入者にとっては、補助制度を活用することで長期的なコスト削減が可能となります。
建設業界が取るべき対応策
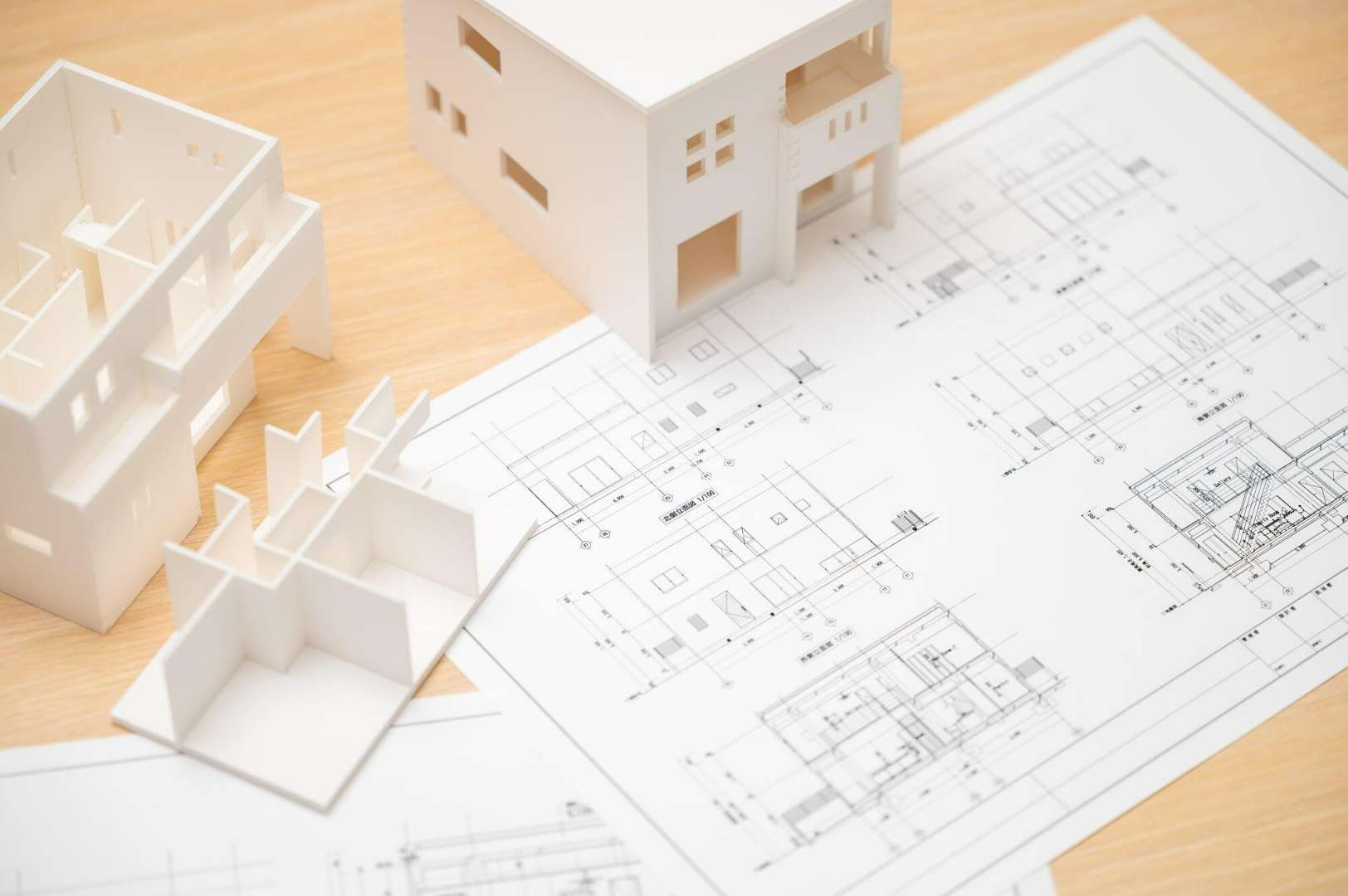
設計・施工における注意点と対応策
建築確認申請の合理化に伴う手続き変更
2025年の建築基準法改正により、建築確認申請の手続きが一部合理化されるとともに、審査対象や提出図書が見直されます。特に、旧4号建築物の一部(新2号建築物)では、構造関係規定や省エネ基準への適合を示す図書の提出が必要となる一方、仕様規定で安全性を確認する場合には一部図書の省略が可能となるなど、変更点を正確に把握する必要があります。設計・施工に関わる事業者は、新たな要件への適合を確認し、適切な書類作成や事前準備を徹底することが求められます。
建築士の業務範囲と責任の明確化
改正後は、建築士の業務範囲がより明確になり、設計・施工に関する責任の所在が厳格化されます。特に、構造安全性や省エネ性能の適合確認において、建築士の役割が拡大する可能性があります。設計事務所や施工会社は、最新の法令を踏まえた実務対応を進めるとともに、建築士への適切な教育・研修を強化することが重要です。
構造計算・安全性確保の新基準適用
構造関係規定の審査対象が拡大され、特に木造建築に関する安全基準への適合確認がより重要になります。旧4号特例の適用範囲が見直され、木造2階建て等(新2号建築物)においても、壁量計算などの仕様規定への適合確認と関連図書の提出が必須となります。また、延べ面積300㎡を超える木造建築物には構造計算が義務付けられます。建築業界は、新基準に対応するための知識・技術を習得し、適切な設計・施工管理を行うことが求められます。
法改正後のビジネスチャンスと課題

脱炭素社会に向けた新たな市場の可能性
法改正により、省エネ性能の向上が強く求められるため、高断熱・高気密の建築材料やエネルギー効率の高い設備の需要が増加すると考えられます。再生可能エネルギーの活用やゼロエネルギーハウス(ZEH)の推進が進む中、企業は省エネ技術を活かした新しいビジネスモデルを構築し、市場の拡大に対応することが求められます。
小規模工事への影響と施工方法の見直し
改正によって、小規模建築物に関する規制が強化されるため、従来は対象外だった工事においても法適合が求められる可能性があります。特に、2階建て住宅や小規模な商業施設の施工において、より厳格な基準を満たすための対策が必要となります。施工業者は、新たな基準に適した工法や材料を積極的に導入し、品質確保とコスト管理の両立を図ることが重要です。
建築法改正に伴う施工管理・検査基準の強化
法改正後は、施工管理の厳格化と検査基準の強化が進み、建築物の品質保証がより重視されることになります。特に、防火性能や耐震性、省エネ基準の適合確認が重要視され、現場管理や書類提出の精度向上が不可欠となります。施工業者や建築士は、現行の検査基準との違いを正確に理解し、新しい基準に基づいた施工管理体制を確立することが求められます。
まとめ
2025年の建築法改正は、建築基準や省エネ基準の強化を含み、業界全体に大きな影響を与えます。脱炭素社会の実現に向け、建築物の安全性や環境性能の向上が求められ、木造建築や防火基準の見直しが設計・施工に直接影響を及ぼします。また、建築確認申請の合理化や省エネ基準の義務化拡大により、建築計画の見直しが必要となります。
一方で、省エネ住宅や木材活用の促進が新たなビジネスチャンスを生み出し、新技術や新素材の導入が進むと期待されます。改正に適応できない場合、建築確認の遅延や設計変更の負担が増すため、事業者や建築士は最新情報を把握し、対策を講じることが不可欠です。2025年4月1日の施行に向け、改正内容を理解し、実務への影響を考慮した準備が求められます。
弊社の特徴として、フレキシブルに現場の改革に取り組んでいます。無駄な時間は作らない方針で、会議や打ち合わせはほとんどなく、無意味な縛りや社内ルールの類もありません。こういった改革とワンストップ体制により、生産性を大幅に向上させることができました。
アート株式会社は、「建築業界のアタリマエを変える」取り組みを行っています!一度、フランクに話しませんか?

さらに福利厚生も充実しており、年間休日は125日以上と、業界トップクラスの働きやすい環境が整っています。しっかり休んでリフレッシュでき、趣味の時間や家族と過ごす時間も作れるので、ワークライフバランスを取りつつキャリアを築くことが可能です。
キャリアにお悩みの方や異業種で働いている方、個人事業主の方、そして再チャレンジしたい施工管理経験者の方、アートで施工管理職として働いてみませんか?
▼関連記事▼
働く前に知っておくべき建設業の2025年問題とは? 今後の影響やアート株式会社の取り組みを紹介!
建設業の週休2日制義務化はいつから始まる? 令和6年から適用される時間外労働規制とは



